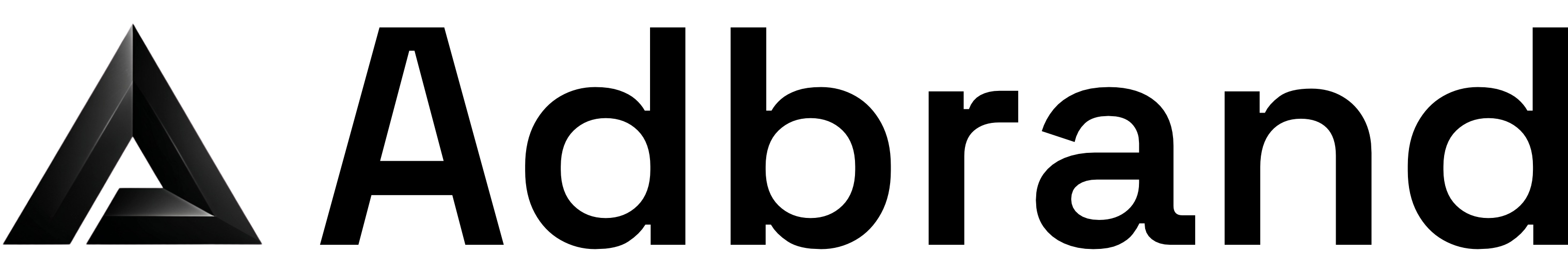近年、生成AIによる動画制作技術は急速に進化しており、テキストや音声から映像を生成するサービスが注目を集めています。その中でもByteDanceが開発した「OmniHuman」は、1枚の人物画像と音声を入力するだけで、実写と見分けがつかないほど自然な人物動画を生成できる点で注目されています。
本記事では、OmniHumanの概要や特徴、料金、使い方、活用事例、注意点を整理し、ビジネスにおける利活用の可能性を解説します。
目次
OmniHumanの概要
OmniHumanは、TikTokの親会社ByteDanceが2025年に発表したデジタルヒューマン生成モデルです。静止画と音声や動画を入力条件とし、AIが人物の動作や発話を自然に再現する動画を生成します。従来のディープフェイクでは大量の画像データが必要でしたが、OmniHumanは1枚の画像だけで十分という点が大きな違いです。 現在は研究開発段階で、ByteDanceのAIプラットフォーム「即夢AI」で限定的にテスト提供されています。

引用: https://jimeng.jianying.com/
主な特徴と強み
OmniHumanは複数の特長を持っています。以下では特に注目すべきポイントを整理します。
高精度なリップシンクと全身動作
音声に合わせて 口の動きを正確に同期させるだけでなく、手や体のジェスチャーまで自然に生成 されます。歌唱やスピーチの場面でも、本人が実際に話しているかのようなリアリティが得られます。従来のモデルで見られた不自然な手振りや口形のずれが改善され、プレゼンテーション動画や教育映像でも安心して利用できる水準です。
マルチモーダル対応
音声、動画、ポーズデータなど多様な入力信号を条件として利用 できます。たとえば音声だけで話す動画を作成したり、既存の動画モーションを模倣した新しい映像を生成することも可能です。条件が柔軟に選べるため、用途に応じて最適な表現方法を選べるのが利点です。
多様な入力への対応
顔のアップ、上半身、全身といったさまざまな画像に対応可能 です。出力動画の縦横比も調整でき、用途に応じたカスタマイズが可能です。宣材写真やプロフィール画像など限られた素材からでも、プロモーションに使える動画が生成できる点はビジネス利用に向いています。
高品質なフォトリアル表現
表情や質感まで細部をリアルに再現 でき、不自然な「AI特有の違和感」が最小限に抑えられています。照明や肌の質感なども自然で、既存の映像と組み合わせても違和感が少ない仕上がりになります。特にマーケティングや広告動画においては、視聴者に違和感を与えないことが大きな価値となります。
料金プランと制限
現段階ではOmniHumanは テスト版として無料で試用 できます。ByteDanceの発表によると、 正式リリース後はサブスクリプション型の料金体系が想定 されており、個人や企業が利用しやすい価格帯になる見込みです。
ただし、正式公開前のため商用利用や長尺動画生成には制限が設けられており、利用規約に基づいてウォーターマーク付きの出力が必須となっています。
活用シーンと事例
OmniHumanは幅広い分野での活用が期待されています。
-
SNSコンテンツ制作 TikTokやYouTubeで写真を動かして解説動画を作成
-
マーケティング ブランドキャラクターや経営者の写真を用いたメッセージ動画
-
エンターテインメント アーティストの歌唱映像や映画の追加シーン制作
-
教育 歴史上の人物を再現した講義動画や語学学習用アバター
-
メタバースやゲーム リアルな動作を持つバーチャルキャラクターの生成
また実際の利用例として、SNS上では 複数の生成AIを組み合わせた制作フロー が紹介されています。
例えばQwen Imageで画像を生成し、MiniMax Speech-02-Turboで音声を作成、その後OmniHumanで人物動画を生成し、Pixverse Lipsyncでリップシンクを調整、さらにGoogle Lyriaで音楽を加え、Claude Codeで制作全体を管理するといった流れです。このようにOmniHumanは、動画制作ワークフローの中核として位置づけられるケースが増えています。
注意点と留意事項
OmniHumanは非常に高機能ですが、いくつかの制約や注意点があります。
まず、現在はベータ版であるため、利用環境や時間帯に制限があり、 全てのユーザーが自由に利用できるわけではありません。
また、悪用防止の観点から、 生成動画には必ずウォーターマークが付与 されます。
さらに、対象は人物を前提としており、動物や非人間キャラクターでは正常に動作しない場合があります。
まとめ
OmniHumanは、1枚の画像からリアルな人物動画を生成できるAI技術です。リップシンクや全身動作の再現度が高く、マーケティングや教育、エンターテインメントなど幅広い活用が期待されます。一方で、まだテスト段階にあるため制限も多く、正式な商用展開は今後の進展を待つ必要があります。とはいえ、映像制作の効率化と新たな表現手法を提供する技術として、今後の動向を注視しておく価値が十分にあるでしょう。